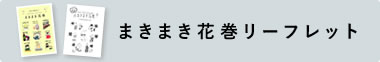東京と花巻の2拠点生活に挑戦中です。
花巻で出会った美味しい物はたくさんありますが、「東和温泉」や「産直あおぞら」などで「きりせんしょ」を見かけると必ず購入し、おやつの定番になっています。
「花巻に来ていない時でも食べたい」と思った時に、「もしや、母が作っていたあのおやつは・・・」と子供の頃の記憶がよみがえりました。
それは巨大な板付きの蒲鉾のような形状で、炊飯器にドンと入れられて蒸され、冷めてから1センチ位の厚さにスライスにするのです。色は濃いめの茶色でクルミは入っておらず切り口には黒ゴマが大量に見えて、あまりモチモチとした柔らかさはありませんでした。噛みしめていると何だか癖になるのか、もう一つもう一つと、たくさん食べていました。
私が気に入っている「きりせんしょ」とはかなり違いますが、お店で買える物も味や形が違うので、あれは我が家のスタイルだったのでしょう。
前置きが長くなりましたが、いつでも好きな時に食べられるよう「きりせんしょ」作りに挑戦です。
母は亡くなってしまったので、残念ながら我が家のレシピで再現する事はできません。ここはまずは基本だろうと、ネット検索した中から農林水産省の「うちの郷土料理 次世代に伝えたい大切な味」の「きりせんしょ 岩手県」を参考にしました。

レシピ通りに・・・するはずが、欲張ってクルミ3割増しで。
うるち粉とクルミは「道の駅 いわいずみ」で見かけて購入した岩手県産です。レシピによれば砂糖200グラムに対して黒砂糖50グラムですが、幼い頃に食べた自家製きりせんしょの記憶から、すべて黒砂糖にしてみました。
なかなか上手く混ざらず、ざらざらした感じでしたが、ぎゅっぎゅっとこねるうちに艶が出てきました。

滑らかになり、艶が出てきました。
生地は一晩ねかせて・・・とありましたが、待てずに4時間で妥協する事に。想像したよりもかなり柔らかくて形づくりに苦労しましたが、なんとか船形にしてお箸で筋を入れて、葉っぱにしました。下に四角く切ったクッキングシートを敷いて、少し離して蒸し器に入れました。
思ったよりも膨らみました。

くっついてしまいました。
完全に冷めてから食べるようにという事でしたが、待ちきれずまだ少し温かい状態で一口。思ったよりもずっと、ペタペタしています。母の大型きりせんしょは冷めてからスライスしていましたが、これはとても包丁で切れそうな感じではありません。

なんとか、それっぽく見えるでしょうか?
完全に冷めてしばらくしてからもう一つ食べました。すると余計な水分がとんだのか適度な固さになり、美味しくなっていました。クルミを増量しただけあって噛むたびに香ばしさが広がり、黒砂糖の優しい甘みも感じます。
レシピによっては、うるち粉ともち粉を混ぜているパターンもありました。確かに、もう少し餅感があっても良さそうです。次回は、クルミとゴマの割合を変えてみたり、もち粉を加えてみようと思います。中に黒蜜を入れてもいいかも。
これでどこにいても、岩手のきりせんしょが食べられます。それぞれの家で異なるレシピや決まった形があるのかな、など興味がわきます。そして、台湾式でお茶を楽しむ時に一口サイズにして可愛いお皿に入れたら、良いかも・・・などアイディアも広がりました。
次は・・・「豆すっとぎ」(豆しとぎ)に挑戦かな?