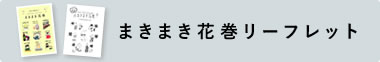里山の風景が残る東和町で。
花巻市有機農業推進協議会主催「農村ワークショップ」が開催されました。
農園を訪問して意見交換をしながら交流を深めるワークショップは、市内でも初開催です。
参加者は、花巻市役所職員や農業者、移住者や市外から幅広く訪れました。
有機農業×地方移住
まず、訪れたのは「ふるまつ自然農園」の双子・古松義彬さんと古松信彬さん。
生まれ育った東京での生活から、オーストラリアやアジアへの旅を経て、農業に関心をもったお二人。
東和町にある「ウレシパモシリ自然農園」での研修を経て、パーマカルチャーと農的な暮らしを実践するため
東京から移住されました。
独立して4年目、無農薬・無施肥の自然栽培で穀物や季節の野菜を育てています。

雑穀の畑

たかきびが立派に育っていました。

自宅前の棚田では、雑草ひとつないきれいな風景が見られました。
広い面積にもかかわらず、田んぼの除草は全て手作業で行っているということにとても驚き、感動しました。
そして、「自然を観察する」
この言葉をとても大切に工夫をしながら農業をされていることが伝わりました。
これからも地域の耕作放棄地を担いながら、理想の暮らしに向かっていく姿を追いかけたいと思います。

次に訪れたのは、「里山耕暮」の佐々木哲哉さん。
福島、沖縄、宮城、各県で様々な農的暮らしから大規模農業法人での仕事を経て、東和町での里山暮らしに行き着きました。
そして、農薬を使わずに岩手では珍しい蓮根とお米を育てています。

きれいな花が咲く蓮田

花は甘い香り、葉はやさしいお茶になり、
実は薬膳にも使用されるほどの栄養価でナッツのような食感、根はよく知られる蓮根に。

どちらも今の水田ではなかなか見られません。
里山耕暮の田んぼは、もしかしたら除草剤や農薬の影響を受けずに種子が眠っていたのかもしれません。
「ただ農業をするだけではなく、田んぼや蓮田といった水辺をつくり、生物多様性を守りながら暮らしていきたい」
そう語る佐々木さんの言葉からは、幼い頃から自然の中で生きものを探し回っていた探検家の姿が今も重なって見えました。
耕作放棄地と持続する暮らし
自宅と蓮田から少し進むと、きれいに整備された棚田が広がります。

しかし、この背景では、さまざまな課題も広がっています。
中山間地域は、田畑が狭く日照りや湿田、法面の広さから見ても効率・機械化農業では条件不利地です。
さらに、少子高齢化によって地域の担い手が減り、耕作放棄地が増えていくなか、
整備には欠かせない草刈り、水源や水路の泥上げ(通称「堰上げ」)や隣接する林地の除伐など多くの作業があります。
本来なら人の手で守っていきたい場所ですが、特に真夏の炎天下での草刈りは体力的にも過酷です。
これまで作業者を支えてきた補助金も廃止されつつあり、やむを得ず除草剤を使ったり、特定の人へ負担が偏ってしまうことが少なくありません。
人手不足と環境への負荷の狭間で、生きものたちの多様性は少しずつ姿を消し、地域の自然の豊かさも薄れつつあります。
参加者それぞれの「なんとかしたい」課題
昼食後は、参加者一人ひとりが農業・地域社会・環境の課題について
「これはなんとかしたい」と思っていることを発表しました。
そしてグループに分かれ、気候変動・水不足、担い手不足、教育・体験、食の安全といった
テーマごとに議論が深められていきました。

様々な意見が出されましたが、以下の意見でまとまりました。
気候変動・水不足グループからは、「水と環境を守り、循環型の農業と暮らしをつくる」
担い手不足グループからは、「新しい人の関わりを広げ、地域全体で担い手を育てる」
教育・体験グループからは、「自然や地域に根ざした実践的な学びで“生きる力”を育む」
食の安全グループからは、「生産者と消費者をつなぎ、地域の食と種を未来へ守る」
それぞれのテーマ別に議論が深められた貴重な時間になりました。
未来への余韻
こうして集まった多様な声に共通していたのは、「地域と自然を守りながら、次の世代に希望をつなぎたい」という願いでした。
課題は決して小さくありませんが、一人ひとりの「なんとかしたい」が集まることで、新しい道筋が見えてきます。
会場をあとにするとき、参加者の心には確かな前向きな余韻が残っていました。