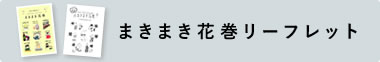台焼の始まり
1895(明治28)年、初代杉村勘兵衛氏が、かつて台温泉で焼かれていた湯ノ沢焼(小瀬川焼)の窯を利用し開窯したのが台焼の始まりである。花巻には磁器の原料となる良質な陶石があったため、産地である有田(佐賀県)で修業した初代により、東北では珍しい磁器の焼き物が生まれた。
器が作られた理由のひとつとして、そこに温泉があったと言う事もあるだろう。料理を盛る器を地元で作るということは自然な事だったに違いない。その後、修業場は有田に留まらず、京都、瀬戸、益子と全国の産地に渡る。昭和に入り現在の花巻温泉に窯を移し、現在は五代目・峰秀氏が製作している。
ガス窯と電気窯を使って作る磁器は、白磁染付(はくじそめつけ:白い釉薬の器に絵を描いたもの)、青磁(せいじ:青色の釉薬の器)、辰砂(しんしゃ:赤い釉薬の器)など。日用雑器、茶器・花器・飾り皿などが多い。

初代の憧れと変わらない想い
台焼の代表が「糖青磁釉」(せいとうじゆう)と呼ばれる薄緑色が特徴の焼き物である。地元花巻では結婚式の引き出物に、また食卓での普段使いにと、ごく自然にどの家庭でも親しまれてきたという。
その中でも、今回は最も古い白磁の染付をご紹介したい。初代、杉村勘兵衛氏の作品に、台焼を語る上で欠かせないモチーフ (絵柄)がある。舟、松、海岸線の柵、そして太陽。
台温泉の狭い山合いで作陶する中、広い海への憧れがこのモチーフを生み出したと五代目・峰秀氏は言う。先代、先先代、と同じモチーフを何代にも渡り今日まで大切に作り継がれてきた。
コバルトと煎茶を煮詰めた「呉須」(ごす)という顔料で染付し、透明な釉薬を付け焼き上げる。磁器特有の澄んだ白にコバルトの青が映える。今でこそ、この白さだが、初期の磁器は陶土の純度が低かったため、灰色がかった生地の製品が多かったそう。熱心な研究により台焼ならではの白磁の染付磁器が誕生した。

今、そして未来へ
台焼には美しい器がある。しかし五代目・峰秀氏はこう言う。「僕は芸術家ではなく職人です。」

日々器に向き合い、同じものを繰り返し繰り返し作る。使いやすく、扱いやすいシンプルな器。それは飾って眺めるためのものではなく、日常に使われるための器。人々の暮らしに寄り添う器である。そうした日々の努力と信念があったからこそ、今日まで永く親しまれて来たのだと思う。
「大変な中に、ちょっとだけそれに勝る喜びがあるから続けられる」と峰秀氏は和かな表情で話してくれた。