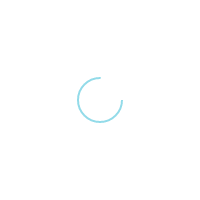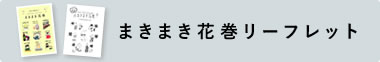100年以上の歴史を持つ染物屋の老舗
花巻市鍛冶町にある「せがわ京染店」は、明治33年(西暦1900年)に町場の染工場として創業しました。
店主は、5代目の瀬川卓哉さん(59歳)。

手ぬぐいから振袖まで、オリジナルの染物ができる「きもの屋さん」として、店舗で染物体験を行ったり、時には花巻市主催のセミナーなどで、子どもたちに講師として染物の楽しさを教えに行ったりしています。また、染色の工芸美術展等に染色の作家として数多くの作品を生み出しています。
瀬川さんは、 東京の大学を卒業してから2年間、京都の染の専門学校で基礎的なことを学び、 それから3年、師匠「奥田祐斎」先生の工房で染色スタッフとして働いてました。祐斎先生は当時から染色業界では風雲児的な方で、既存の染技法のほか、自らが編み出した技法を使って、きものや帯を染めてました。独自の染色技法を10種類くらい開発してる染師です。
そんな先生の下で働くことになった為、当時京都ではまだ、「10年徒弟制度」で弟子を育てる所も多い中、いきなり本番の染を実戦し、染技術を身につけていったそうです。
実家との都合もあり工房は3年で「卒業」し、地元花巻に戻り、30年前に現在の家業を継ぎました。
宮沢賢治の作品の色彩
花巻市は、詩人・童話作家「宮沢賢治」の故郷です。
瀬川さんは、大学時代のゼミの先生(色川大吉氏)から、日本近代史における宮沢賢治の重要性を教えてもらったこともあり、故郷・花巻を離れて、改めて宮沢賢治の魅力に気付かされたといいます。それから、京都で染物の仕事につきながらも、折に触れ賢治作品を読み続けました。
そして、その後の自身の作品にも大きな影響を与え、生み出したのが「銀河夢小紋」。

▲手前が「よだかの星」、奥は「銀河鉄道の夜」をモチーフにしています。
宮沢賢治は、目で見た色に対して「匂いがする」「音が聞こえる」、といった“共感覚”を持っていました。
「共感覚とは」
外部からの刺激はその性質によって、色や形は眼、音は耳、匂いは鼻、味は舌、触感は皮膚というように、別々の器官を通じて認識されます。ところがごくまれに、一つの刺激に二つ以上の器官が反応し、感覚が混合してしまう性質をもつ人がいます。この感覚が共感覚です。幼少期、だいたい三歳くらいまでは誰もがもっていた感覚であるとも言われており、大人になっても維持する人は、芸術方面などにその感性を活かす場合が多々あるということです。
(「天才・宮沢賢治が持つ感性の不思議ー「共感覚」とは何か /NHKテキストビュー」より一部抜粋)
「銀河鉄道の夜」「よだかの星」は、いずれも宇宙にまで繋がっている世界です。瀬川さんは、そんな賢治の世界に広がる宇宙の無限さに、「染」の表現でインスピレーションを得ていきました。同じものを作り続けるのではない。その時の「季節」「空気」「感情」で生まれる、たったひとつの一枚を作りたいという想いが形になりました。

▲作品の色彩を見た時に、音楽が聞こえるようなものを作りたい。
自分だけの一枚を生み出す楽しさ
今回は、取材と同時に「ぼかし染め」を体験してきました。水で濡らしたさらしを適度に絞り、刷毛を使って染色する方法です。体験としてこの染め方をできるところは、あまりないだろうという事です。


あまり考えずに素早く染料をのせていくのがコツなのだそうです。

広げると、そこには偶然が生み出した世界が鮮やかに広がりました。綺麗なところも、濁った部分も、引き立てあってとても美しいです。
その他にも、広げた状態にして刷毛で色をのせていく方法や、さらしを三角形に折って辺の部分に色を着けていく方法も体験しました。




後日、自分で染めたハンカチに、手作りの消しゴムはんこを押してみたらとても可愛くなりました。まるで、賢治さんの童話「十力の金剛石」の世界のようです。
※布用のインクなので、当て布をしてアイロンをかければ、洗濯しても落ちません。

これからのものづくりの可能性をつくる
現代では、和装を普段着とするひとは少なくなってきました。専門的な技術を身につけるために10年修行をするのが当たり前だった頃と違い、数をこなすだけの仕事がないことも現状です。日本が誇る素晴らしい技術を引き継いでいくことが難しくなっている現実は、染め物の世界に限らず、花巻の伝統工芸のほとんどに共通しています。
今求められている人は、ものづくりに関心を持ち、使ってくれるひとのことも考えた「橋渡しができるプロデューサー的な人材」です、と瀬川さんは語ります。

「関心があるひとだけでなく、関心のないひとに、もっと身近に感じてもらえるものづくりができるように、作り手も考えていかなければならないんです。様々な使い方の提案から考えて、販売までをプランニングすること。また、そういう人材も仕事として求められています。」
瀬川さんは、伝統を活かしながら新たな創作も続け、次へと繋いでいくためには、作り手と膝を割って語り合い、これからの道や展望を考えてくれる人材も必要なのだといいます。それを聞いた時、とても胸が熱くなりました。次の世代に求める課題を見据え、決して立ち止まらない前向きな姿勢。
ただ求められるのではなく、瀬川さんの、「こんな若者が必要なんだよ」というメッセージは、きっと今を生きる若いひとたちの心に届くのではないでしょうか。